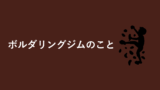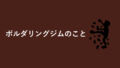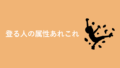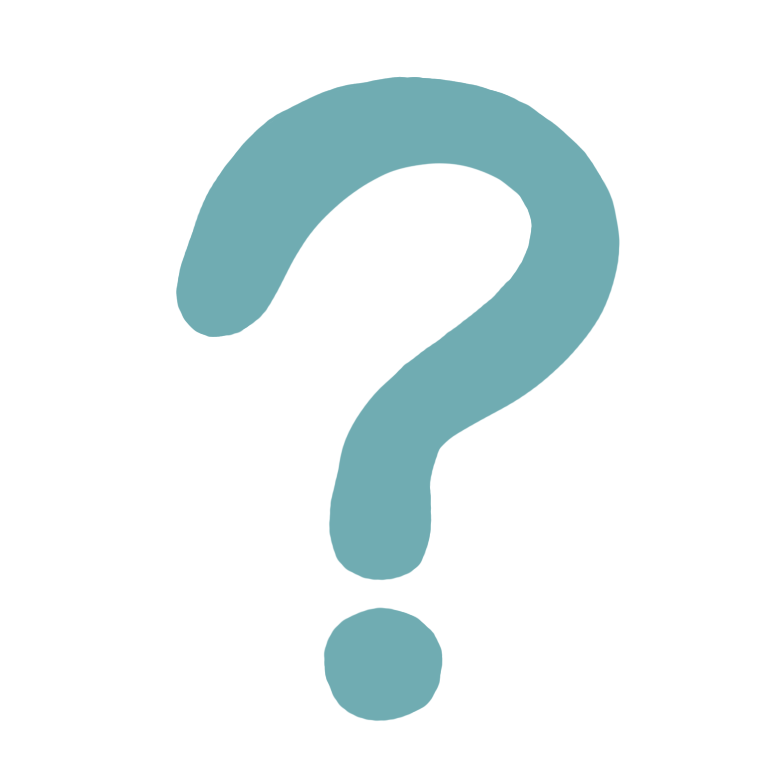
- ボルダリングってだいたい何歳からできるの?
- 早く始めたほうが上手くなる?
ジムでよく、お子さんにボルダリングを始めさせたいという方からこんな質問を受けます。
子どもの運動神経や集中力を育てたいと考える保護者の方にとって、ボルダリングは近年ますます注目されているスポーツのひとつです。そして大人の目線で考えると、スポーツは早く始めたほうが良いんじゃないか、そのほうが上手くなるんじゃないかと思いますよね。
実際のところボルダリング(クライミング)については、始めるなら早ければ早いほど良いとは限らないな、と感じる場面も少なくありません。
ボルダリング(クライミング)に限らずスポーツ全般において、小さな頃から始めることで運動能力を高めると言われる一方、スポーツ活動の低年齢化・競技特化の傾向も危惧されています。クライミングも、特に東京オリンピック以降、どんどん低年齢化してきている印象はあります。
この記事では「ボルダリングは小さいうちから始めるほうがいいか?」「小さいうちから取り組むことで気を付けることはあるか?」ということについて、ジムの現場から感じることをお話ししていきます。
これは、ジムにより課題傾向や方針・キッズスクールの有無を含め考え方は千差万別、そして「お子さんによりけり」の個人差がとても大きいテーマですので、もちろんすべての方に同じく当てはまるわけではありません。
あくまで、検討材料のひとつとしてお読みいただければ、と思います。
▼「ボルダリング」で検索!
もくじ
- そもそも、利用可能年齢はジムによって違う
- 【何歳から?】=年齢より、理解力と自発性がカギ
- 小さな子のボルダリング、気を付けてあげてほしいこと
- 【無理のないスタートのために】まずは「楽しくなること」から
そもそも、利用可能年齢はジムによって違う
日本では、都市部にはもちろん無数のボルダリングジム・クライミングジムがありますし、地方でも複数のジムがあることも珍しくありません。
利用可能年齢はジムによっていろいろ。年齢制限の無いところから中学生以下は登れないところまで様々です。
たいていのジムは、ホームページやSNSなどで利用可能年齢や利用条件などを公開しています。
ちなみに、ほぼすべてのジムが、少なくとも小学生のうちは必ず毎回保護者の見守りが必要です。
中には、中学生も保護者同行必須のジムもあります。
主に以下の点が、ジムにより変わってきます。
条件によっては利用ができないこともありますから、必ず事前に調べましょう。
- 何歳から利用可能か
- 保護者も登る必要の有無
- キッズスクールの有無
- スクールに入る必要の有無
- シューズは借りられるか持参か
- お子様の利用可能時間帯
- お子様のご利用上のルール
- キッズエリアやキッズ壁、キッズ課題の有無
- 見守りのみの保護者の入場料の有無
お子様の利用時間帯などの制限
お子様もどの時間帯でも利用可能というジムばかりではなく、たいてい利用可能時間帯が決まっています。
「スクール生のみ利用可」とか「保護者がクライマーの場合のみ利用可」などの利用条件があるジムも。
これは、クライミングが高所からの不意な落下が前提としてあり、特に人と人との衝突事故は時に生命にかかわる事態にもなり得るくらいの危険性を含んでいるから。
ボルダリング壁は2階くらいの高さがあり、そこを登っている下に小さい子がいるところに(←登っている人の下を通ることはルール違反)万が一大人が上から落ちてしまったら…想像でもその怖さがお分かりいただけると思います。
大手ジムなどのキッズ専用エリアがきちんと区切ってあるところは別として、日本では個人経営の規模の小さなジムが多く、体の大きな大人と小さな子どもが混在して壁を利用することが多くなっています。
特にクライミングに慣れていないお子さんの場合、登っている人の下に不意に入ってしまったり楽しくなって大声ではしゃいだり、付き添いの小さなお子様がマットに上がってしまったりということもよくあります。
保護者の方の中にも危険性の認識が薄い方もあり、何度もスタッフがお声掛けしても危機管理ができない方も正直なところ少なくありません。(お子さんが登っているのにスマホを見ているというのは完全にアウトです)
状況によっては、周りの人がいつも以上に注意を払うことで事故を防いでいる場面も多く見られます。
そこで、お子様のご利用時間などに条件を付けることで、安心・集中して登れる時間帯や環境を確保する、ということです。
ジムによっては、「この子はきちんとルールやマナーを守って利用できるから大丈夫」と判断すれば他時間の利用を許可することもあります。テストを受けて合格したら許可、というようなジムも。
利用可能年齢なら課題も登れる?
ジムの利用可能年齢と課題の難易度とは比例していません。
小さい子も利用可能だけれども大人と同じ課題をそのまま利用する、というジムもあるように、あくまで「ジムを利用可能ですよ」という規定です。
対象年齢って書いてあるからひとまずある程度登れるだろう、というのとは違います。
つまり、
- 「ジムの最小利用可能年齢=始めるのに最適な年齢」
- 「ジムの最小利用可能年齢=その年齢向けの課題」
ということではありません。
そのあたり、下記でもう少し詳しく触れていきますね。
【何歳から?】=年齢より、理解力と自発性がカギ
ジムに来られるお子さんを見ていて思うのは、上達するかどうかは「何歳から始めるか」ではないのだな、ということ。
大事なのは、「課題を攻略するのが楽しい!」「もっと登れるようになりたい!」というお子さん自身の気持ちだと感じます。
例えば身近には、一般的にスポーツを始めるには遅めと思われる中学生くらいから始めて、現在はかなりのレベルで活躍している選手も何人かいます。
彼らに共通しているのは、自分の意志で始めていて、「クライミングが楽しい!」という気持ちをずっと持っていること。
誰かに言われてなんとなく競技を続けているのではなく、自分が楽しく登っている結果が競技結果に表れている、ということなんだなと思います。
逆に、未就学の頃や小学校低学年頃からずっと競技で登ってきて中学校入学を機に辞めてしまう子、というのも多く見ています。
そしてその場合、競技としてのスポーツクライミングを辞めるというだけでなく、二度とジムにも来なくなってしまうことが多いです。
競技じゃなくても趣味で登りに来たらいいのになあ…と思いますが、悲しいことに完全に離れちゃうケースが多いですね。
「順位を競うクライミングがいつの間にか辛いものになってしまって、楽しさや登る意味を見出せなくなってしまう仲間も、周りにもたくさんいた」と、大学生まで競技選手を続けてきた子が話してくれたことがあります。
理解力:スポーツとしてのルールを楽しめるか
「ボルダリング」のスポーツとしてのルールを理解し、その中で楽しめるかどうかというのは、ボルダリングの継続や上達にとって年齢よりも大きな要素です。
ボルダリングは「壁の下から上まで登れればOK」というわけではなく、スポーツとしてのルールがあります。
- 指定されたスタートの条件で身体が保持できてからスタートすること
- 決められたホールド(石)だけを使って登ること
- ゴールホールドを両手で保持して完登とすること
年齢が低くても、たとえば年中さんくらいでも、このルールをしっかり理解して楽しんで取り組める子はいます。
(ただしそれより小さい年齢だと、ルールを理解して登るにはさすがにまだ難しいところがあるかな。)
でも、もっと年齢が大きくても、ルールの中で登ることを楽しめない子ももちろんいます。
うちのジムにくるキッズのお話。
年中さんのAくん。それまでは別のところで登っていましたが、そこでは小さい子は「課題」ではなく「自由に上まで登ってみようね」というスタイルだったそうです。
親子ともどもそういうものだと思って通っていたけれど、たまたまうちのジムに来てみたら「課題」というものがある。
年中さんの彼にとって、それが新鮮で、難しくて、とても楽しかったようです。お父さんに「課題ってゲームみたいで楽しい!もっと登りたい!」と訴え、こちらに通ってくれるようになりました。
Bくんは小学校2年生。お父さんやお母さんと一緒にうちのジムに通い始めましたが、彼にとっては逆に「課題」が縛りになってしまっているのが、見ていてよく分かりました。
最初の数分は課題を登っても、少しして集中が切れてしまうと「もう何でもいい!」と言って課題関係なくフリーで登っていくという日々が続きました。
お父さん・お母さんは数カ月間頑張って声掛けをし、一緒に通われていましたが、様子は変わらず。
そしてAくんがもともと通っていたところに通い始め、こちらには来なくなってしまいました。
このように、年齢というよりも、本当にお子さんによっての個人差が大きいです。
どちらが良い悪いということではなく、お子さんのその時の様子によって相性の良い場所で楽しむのが良いのではないかな、ということです。
「決まったのしか使えないなんて楽しくない!好きに登ろーっと!」と課題(ルート)関係なく登る子は、小学生くらいならザラにいます。
何度かジムに通ってさりげなく促してみてもそんな様子が続くなら、「ジムで登る」「ボルダリングを楽しむ」ということがその子にとってはまだ少し早いのかもしれません。
「ルールの中で決まったルートを登ることに窮屈さを感じてしまっているかもしれない」
「まだアスレチック施設やレジャー施設で“上に登る“ということを楽しむほうがいいのかもしれない」
という判断の目安になると思います。
あ、もちろんジムで「課題じゃなくても自由に登ったらいいよ!」と言ってくれる所なら、ぜひどんどんそれで楽しんでください!
でもぜひ、いつかどこかのタイミングで、「課題を登る」ということにシフトできるように促してみてあげてくださいね。
ボルダリングは、自分の頭で考えて自分の身体だけを使って行うスポーツ。ルールの中で登ってこそ楽しいスポーツです。
本人が気乗りしないまま漫然と続けても、なかなか上達できるものではないんですよね。
もう少し大きくなるまでいったん待ってみることで、今度はもっとルールの理解が進み、楽しめるようになるかもしれません。
年齢を目安にするのではなく、お子さんの様子を見て「今、始めどきかな?」を判断してあげてください。
自発性:「もっと登りたい!」は最大の才能
何度も言いますが、ボルダリングは自分で「登りたい!課題を攻略したい!」と思えることが一番のスタートラインであり、最も大切なことです。大人も子どもも同じ。
ジムに来るお子さんを見ていても、登ることが楽しくなってきた子は目が輝いていて、見ていてすぐわかります。
自分にとって少し難しい課題に何度落ちてもチャレンジする子、登れない時に自分なりに考えて工夫しようとする子などは、自分の中に「この課題を登れるようになりたい」という気持ちをしっかり持っています。
年齢的に早い子なら年中さんくらいでも、自然と「登れない、じゃあどうしたら登れる?」と考え工夫しようとします。
そして登ることが大好きな子は、「新しい課題できてるよ!」と言うと、「やったー!楽しみ!」とワクワクしたとっても良い顔をします。
これも、子どもだけでなく大人も同じ。
逆に、誰かに言われてなんとなく登りに来ている子は、何度来店しても自分で考えるというより「次はどこ?」「その次は?」と誰かがホールドの場所を教えてくれるのを待っていたり、登れる課題ばかりを繰り返して他の課題には手を出さなかったり。
明確に「もうイヤだ!」「怖い、絶対にもう登りたくない!」と声を出す子もいます。
そんな様子が続いた時は無理をせず、お子さんがもう少し大きくなってから改めて挑戦することで、もしかしたらまた楽しさの感じ方が変わるかもしれません。
もちろん、最初は気が進まなくてもやっていくうちに楽しくなるケースも無くはないですが、…見ていて多くはない印象です。
ちなみに、高さが怖いのは大人でも怖いです。でも、ハマっている子は怖いながらもチャレンジします。
上の項でも書きましたが、ボルダリングは自分の頭で考えて自分の身体だけを使って行うスポーツ。本人が気が進まないのに登らせ続けたところで、うまく登れるようになるものではありません。
「保護者さんの手を引っ張って楽しそうにジムにやってくる」お子さんは、やっぱり伸びるスピードも違います。
始める年齢が重要なのではなく、何歳で始めてもまずは「楽しい!もっと登りたい!」という気持ちを育てることが、ボルダリングが上手くなることには何よりもとても大事です。
どうしたらその気持ちを育てられるのか。
私が思うのは、「保護者の方の力は偉大だ」ということ。
下の項で、保護者としてどうしたらよいか、ジムでいろいろな親子さんに接する中で感じることを書いています。
これもすべての子に当てはまるわけではありませんが、ご参考になれば幸いです。
小さな子のボルダリング、気を付けてあげてほしいこと
小さい時から特定のスポーツだけ、ボルダリングだけに絞ってガンガンやり込むより、できるなら公園や原っぱで自由に走り回って身体をいっぱい使って遊んだり、いろんなスポーツを体験したりするほうが、全体的な身体能力の獲得・向上には良いと言われています。
まず大前提としてそのことを知ってくださった上で、ボルダリングをする時に気を付けるといいんじゃないかなということをいくつか書いていきますね。
あまりにも怖がっていたら、決して無理しないで
お子さんが「怖いからもう絶対に嫌だ!」と強く強く拒否しているようなら、けっして無理強いはしないで欲しいな、と思うのです。
高く足元が不安定な所に立つボルダリング。
上に登ると、下から見て想像するより何倍も怖いものです。大人でも怖く感じる高さ、小さなお子様にはその何倍にも感じます。
ジムでは、もちろん楽しんで登る子もたくさんいる一方で、「もういやだ!こわい!絶対に登らない!」という小さなお子さんの悲鳴のような声と、親御さんの「怖くない!登れ!」と少し怒気を含んだ声の応酬、という悲惨な状況を見ることも珍しくありません。
もちろん怖い中でも頑張って登れたらすごい成功体験に繋がるし、お子さん本人にも大きな自信になります。
でも、もし本当に恐怖を感じているところに「怖くない!ほら登れ!」とあんまりにも無理強いしてしまうと、「嫌だ、絶対にもう二度とやらない!」という“完全拒否”に繋がりかねません。
それってすごくもったいないなあと、見ていて思ってしまうのです。
今回は無理せずここまでにしておいて、もう少し学年が大きくなってからまたチャレンジしてみたら、今度は楽しく登れてクライミングが好きになるかもしれないのになあって。
高学年に向かっていくと背やリーチも伸びて、少し人生経験値も増え、怖さの感じ方がまた違ってきます。
「恐怖」という感情は、人間の危険回避のための防衛本能。
「怖くない」は無いです、大人でも怖いです。
どう頑張っても怖いもんは怖い。
その感情は、まず認めてあげて欲しいなと思います。
そして頑張れた時は、「ほら怖くなかったでしょ」ではなく、“怖かったけど頑張ったこと“をしっかり褒めてあげてください。
身体の状況をよく見て気を付けてあげて
子どもの身体って、大人とは全然違い、スポーツをした後に乳酸が溜まりにくいそうです。乳酸は生成されるけれども、分解されるのがとても速いとのこと。
だからどれだけ登っても体力無尽蔵のようにいつまでも動き続けられるし、疲れても次の日にはケロッとしてたりする。
それが、羨ましいところでもあり、怖さでもあります。
クライミングは、日常生活ではそこまで使わない関節や腱に大きな負担のかかるスポーツです。
“筋肉痛”で疲労を教えてくれる筋肉と違い、関節や腱はなかなか疲れを自覚することができず、痛みが出てきたときはすでに故障状態となっていることも。しかも、一度傷めてしまうとなかなかすっきり回復できなくなってしまいます。
大人の関節・腱と比べて小さくやわらかな子どもの関節・腱は、いくら体重が少ないとはいえ掛かる負担は大きいもの。
そしてそれをお子さん本人がなかなか自覚できません。
「今日も登りに行く!」「今日も!」と何日もぶっ続けでジムに登りに来たりする子もありますが、そんな時は保護者の方に「少し身体を休めたほうが良いですよ」とお話ししたりします。
たいてい「本人が疲れてないって言うので大丈夫です」と言われちゃいますが…
前述のように、子どもの身体は、疲れたという自覚を持ちにくいにもかかわらず関節や腱には大きな負担がかかっているもの。
その自覚のない疲れや負担が積み重なることで「オーバーユース」という状態になり、故障に繋がりかねません。
1日酷使したら1~2日関節や腱・筋肉を休ませることで「超回復」という状態になり、むしろ強くなると言われています。
お子さんは多分「疲れてないから登りたい」と言いますが、そこは大人が少しコントロールしてあげてください。
ジムでは、お子さんには「休息(レスト)を上手にとるのも上手いクライマーの技術なんだよ。」なんて、ちょっと自尊心をくすぐるような言い方をしてみたりします。そうすると受け入れてくれることもあるので。
また、小さいときから続けていく中で、中学生くらいで男女とも急激に身体が変わる時期がやってきます。
大人の身体に少しずつ近くなって、体重も重くなり、重心なども変わります。
その時にそれまでの体重が軽い身体のやり方で登り続けていると、身体に無理が積み重なり、故障に繋がってしまうこともあります。
どのスポーツでも難しい時期になりますが、大人に近くなった身体の使い方を習得し変化させていくことが大切になってきます。その時期は、しばらく前みたいに登れなくなってしまうかもしれません。
でも先を見据えれば、ここで身体と相談しながら少しずつ順応させておくことが大切。
「何で登れないの?前なら登れてたでしょう?」と言いたいところをグッと抑えて、様子を見てあげてください。
何か今までと違う…と、本人が一番戸惑っているかもしれません。
子どものうちから故障を抱えて登ることだけは避けたいもの。
本人は登ることに一生懸命でなかなか客観的に自分の身体の状態を見ることは難しいものです。
ぜひ保護者の方がよく様子を見て、必要なら休ませてあげるように促してみてください。
レストや状態に応じた変化も、上達のための大事な技術です。
【無理のないスタートのために】まずは「楽しくなること」から
『年齢を見るのではなく、ほかの子と比較するのではなく、お子様自身の姿を見て』
年齢的に早く取り組むことよりも、これが直接上達に結びついてきます。
何よりまず保護者の方の寄り添いで「登ることが楽しい!」という気持ちをしっかり育ててあげてください。
それがしっかりと太い根っこになり、根っこが太ければグングン枝葉も伸びていきます。
そして、保護者の方自身がお子さんが登っている姿を心から楽しむことが、栄養や水やりになっていきます。
ぜひ一緒に、楽しんでください。
下記のサイトでは、「ボルダリング」で検索すればいろいろ出てきます。
ここに登録されている施設はアミューズメント施設やアスレチック施設から専用ジムまで幅広く、例えばボルダリング専用ジムも初心者の方大歓迎!で入りやすいところが多いと思います。
調べて、ぜひ行ってみてくださいね。
楽しい時間を!
\ボルダリングジムもたくさん載ってます!/