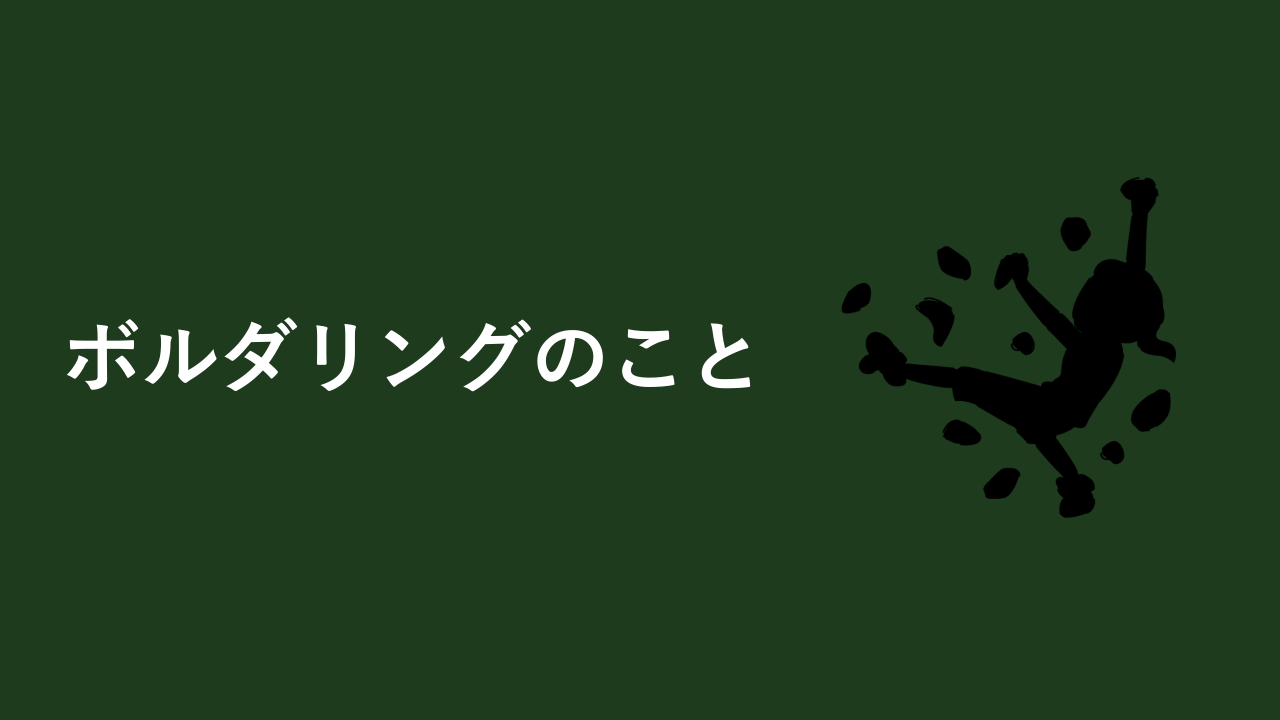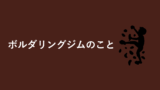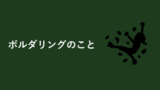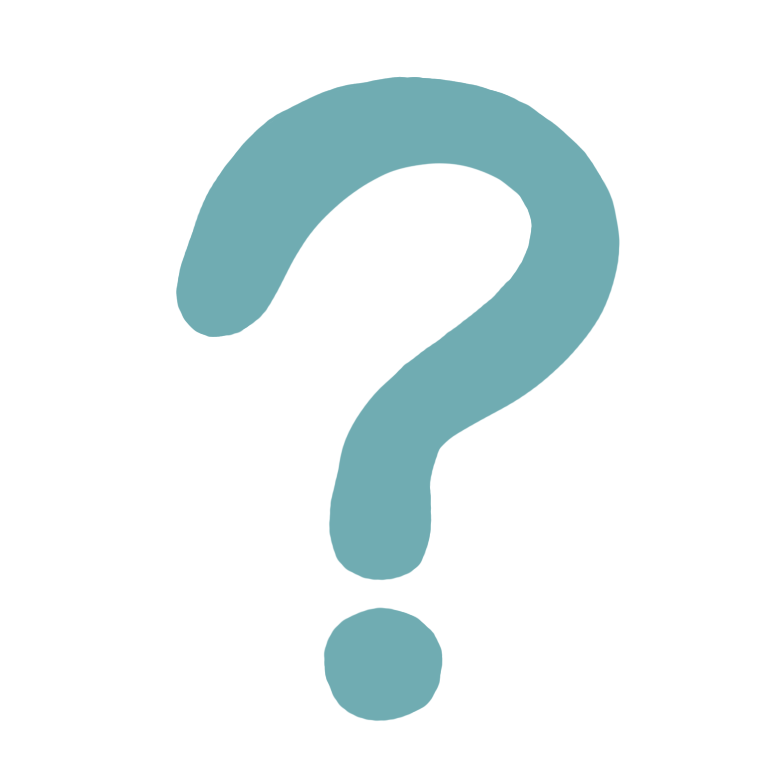
- 「クライミング」と「ボルダリング」って違うもの?
- 壁の低そうなやつと高いやつはまた違うの?
- 「ボルダリング」と「ボルダー」の違いは?
- スピードって誰でも挑戦できる?
オリンピック競技にも定着し、「クライミング」という言葉を耳にする機会も目にする機会も増えてきましたよね。
でも、「ボルダリング」や「リード」、「スピード」、さらには「ボルダー」という言葉もよく聞きます。
これって具体的にどう違うの?と思われている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、クライミングのさまざまな種類「ボルダリング・リード・スピード」について、初心者の方にもわかりやすく、違いについて少しご説明しますね。
▼「ボルダリング」で検索!
もくじ
すべてをまとめたものが「クライミング」
簡単に言うと総称が『クライミング』で、その中に「ボルダリング」「リード」「スピード」の種目があるということになります。
ちなみに「ボルダー」は「ボルダリング」の国際共通名称。日本国内だとまだ「ボルダリング」のほうが多く使われている印象ですので、「ボルダー」でも「ボルダリング」でもどちらでも通じます。
クライミングはもともと、山岳登山技術の中の岩壁を登るためのトレーニング、いうところから始まったものです。
その後、それを競技化する流れができ、現在では力を発揮する場所として
・ジムでのトレーニング+外岩登攀
・競技としてのクライミング(大会出場)
・趣味としての屋内ジムクライミング(外岩には登らない・大会にも出ない)
ざっくり言えばこのように分かれていて、この中で「屋内ジムで登って楽しむ」という方が圧倒的に多いと思います。
屋内ジムの課題(ルート)も、課題によって「外岩クライミングのトレーニング」や「競技クライミングのトレーニング」に寄っていることもあります。
ジム自体がどちらかの傾向に寄っていることもありますし、それぞれの傾向の課題が混在しているジムもあると思います。
そういうジムそれぞれの傾向については、別の記事で書いていますので、よろしければご覧ください。
ちなみにこのブログでは「屋内ボルダリング」についての記事を主としていますので、リード・スピードについては概要だけ、また外岩のことについては割愛します。
ボルダリング(ボルダー)
高さ約4m程度の壁にホールドと呼ばれるカラフルな石が付いていて、ハーネスやロープ、ヘルメットなどの安全器具を着けずに登っていくものです。生身で落ちてもある程度は大丈夫なように、ジムでは下に分厚いマットが敷いてあります。
クライミングの中で一番街中に専用ジムが多く、身近で体験しやすいものになります。
「ボルダリング」と名の付くところで思いつく施設は
・ボルダリングジム
・公園などの遊具
・レジャー施設
などいろいろありますが、本当の意味での「ボルダリング」ができるのは「ボルダリングジム(クライミングジム)」になります。
本来の意味での「ボルダリング」は、難易度によってあらかじめホールドをセットした「課題」と呼ばれるルートを登ること。そしてジムはその課題を提供し登ることのできる場所、ということになります。
なので、ほとんどの公園遊具やレジャー遊具は「ボルダリング“風”遊具」ということになります。
意外に「ボルダリング=壁をてっぺんまで登ること」と思っている方も多くあり、ジムとそれ以外の施設を混同されている方もありますので、別記事でボルダリングのできる施設あれこれについて深堀りしますね。ぜひ読んでみてください。
ちなみに外岩でも、ハーネス・ロープを着けずに岩を登るタイプを同じく「ボルダリング(ボルダー)」といい、持ち運び用のマットを敷いて登ります。
元々「boulder=大きな石」を登るということで、日本ではing形で「bouldering(ボルダリング)」と呼ぶのが一般的でしたが、IFSC(国際スポーツクライミング連盟)の使用している名称が「boulder(ボルダー)」だったため、日本でも2023年から「ボルダー」に統一することとなりました。なので「ボルダリング」イコール「ボルダー」です。
ただ、まだ日本では「ボルダリング」「ボルダリングジム」のほうが一般的には多く使われていますので、安心して「ボルダリング」という言葉を使ってください。
リード
ボルダリングと違うのは、ハーネス(安全帯)を腰に着用しロープで安全確保しながら10m以上もある高い壁を登っていくこと。
この方式のクライミングを「ルートクライミング」や「ロープクライミング」といいます。
その中でも大きく下記の2種類に分かれます。
- 「トップロープクライミング」
あらかじめそのルートの最上部の支点にロープが掛けられ、安全確保された状態で登っていくクライミング。これはほとんどの場合初心者の方が行うスタイルで、一般競技の種目にも無いので、聞き馴染みがないかもしれません。
ただし、手足や視力に障がいのある方の「パラクライミング競技」においては、このトップロープクライミングのみが正式種目となります。 - 「リードクライミング」
クライマー自身が、ルートの途中に設置してある支点のカラビナにロープをかけながら登るスタイル。
競技では、「ゴール」はトップのホールドを掴むことではなく、最上部のカラビナにロープを通すことでゴールが認められます。
リードクライミングは陸上競技でいうと「長距離走」。持久力が必要不可欠な種目です。
トップロープもリードも、クライマー1人で行うものではなく、下でロープを操作して安全確保(ビレイ)する「ビレイヤー」が必要になります。
ですので、「オートビレイ」という自動でビレイしてくれる機械が設置してあるジムじゃない限り、外でもジムでも2人以上いないとできません。
またビレイヤーにはクライマーの安全がかかっていますので、ジムでリードをする場合はだいたい「ビレイヤー研修」を受けて合格した場合のみ利用できるようになっています。
≪警告!!≫
以前私の働くジムに、「ネットで動画を見て、友だちと見よう見まねで外岩でトップロープクライミングやってます。グループに誰も経験者はいなくて、師匠は動画です」という人が来たことがありますが、心底驚きました。危険極まりないです。
なんと、お子さんも一緒にやっているとのこと。
なんていうかもう…言葉を失いました。
命がかかっていますので、ネット動画で見よう見まねなんて、絶対に絶対に絶対にやめてください。
ハーネスやロープ、カラビナなどは、すべて命を守る道具です。
しっかり技術がある人と一緒に行って、その技術を受け継いでください。
ちなみに、その人はジムでのボルダリングも初めてで、初級課題も登れませんでした。
人生最初のクライミングが、グループの誰も経験なくネット動画の見よう見まね外岩トップロープという…
無謀すぎて怖くてびっくりしました。
世の中にはそんな人たちもいるんだな、ちゃんと啓発しないといけないな…と思った出来事でした。
(その方はその後ジムには一度も来ませんでしたし、紹介したロープクライミングの講習にも一度も顔を出していないそうです。)
スピード
スピードは、世界共通のホールドを共通配置した壁を使い、スタートからゴールまでのスピード対決をする種目です。ビレイはオートビレイ機を使うことになります。
陸上の100m走のようにタイムが早いものが勝ち!という競争の世界なので、オリンピックなどで見ていて、クライミングをしたことのない人でも一番分かりやすい種目です。
でも、スピード壁自体が全国でも限られた場所にしかなく、一般の方がスピード種目を体験できる施設は国内にはほとんどありませんので、一番体験することのできないクライミングでもあります。
競技選手の人数も少なく、まさに短距離走の選手のようなフィジカルのすごい選手が多いです。
それぞれの種目のことをよく知れば、観戦ももっと楽しめます
このように、ひとくちに「クライミング」といってもいろいろな種類があり、それぞれ見どころが違います。
それぞれの種目のことを知ることで、オリンピックなどでの観戦ももっと楽しめるようになりますよ!
そして、身近で気楽に楽しめるボルダリングも、ぜひやってみてください。
その楽しさ・奥深さ、そしてきつさ・難しさも、たくさんの人に体感してもらえたら嬉しいなと思います。
\ボルダリングジムもたくさん載ってます!/