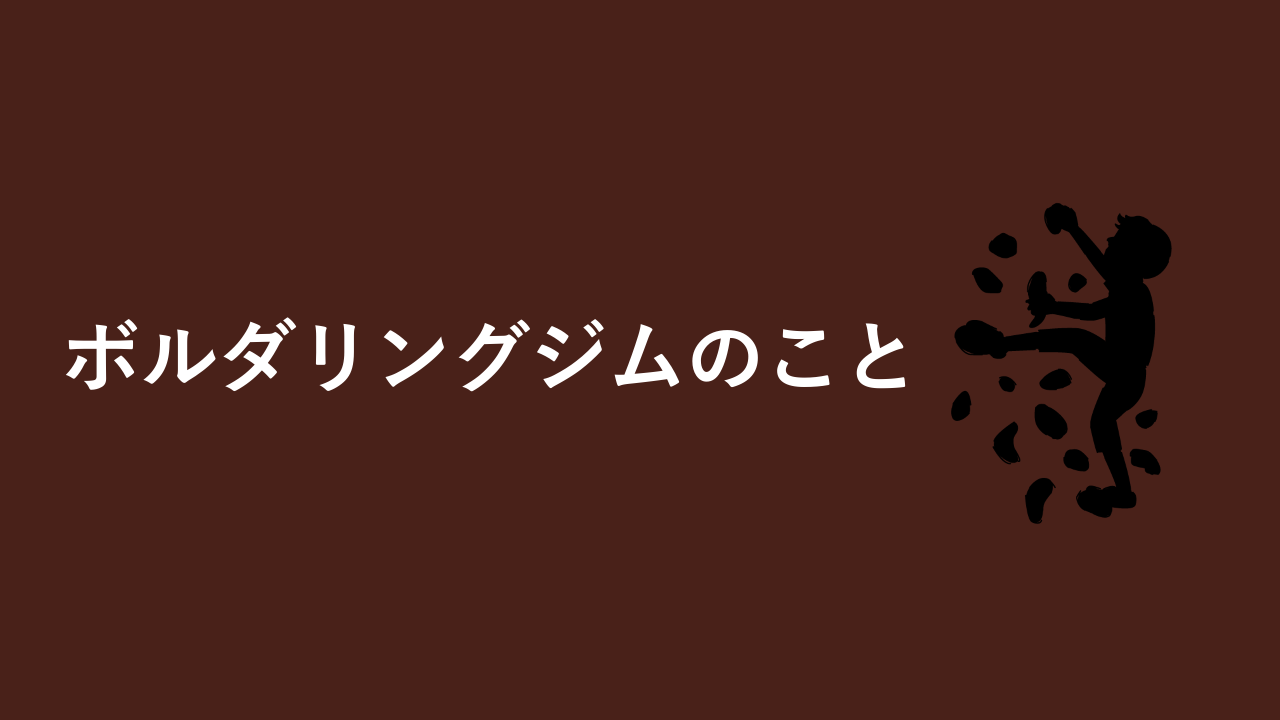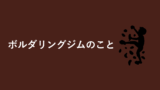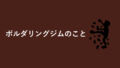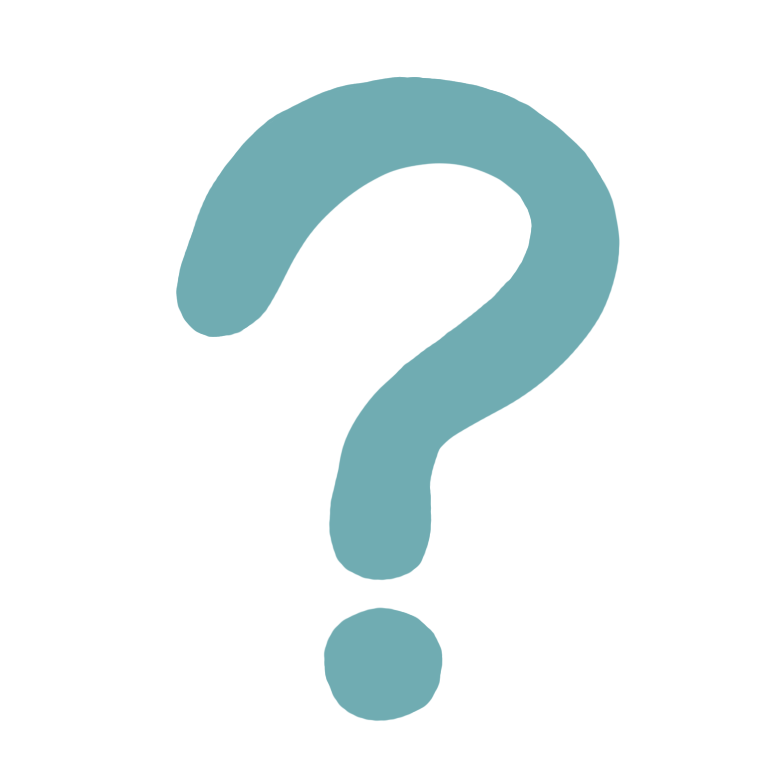
- ボルダリングジムってどこに行っても同じようなもの?
- 何かジム別の違いがあるの?
いまや小さな街でもひとつは、都市部なら無数にあるボルダリングジム。
壁があって、ホールドが付いてて、マットがあって…という基本はどこのジムも同じです。
どこのジムに行っても設備や課題の難易度は同じようなものなのかな?と思われがちですが、実は設備も課題の難易度やタイプも、本当にそれぞれの店舗でまったく個性が違います。
ボルダリングジムにとって、『課題』こそが主力商品そのもの。
主にここで個性を出すことで、他ジムとの差別化を図っています。
分かりやすく飲食店で例えると、「カレー屋」と一口に言ってもそれぞれ個性がありますよね。
辛さもいろいろ、インドカレーなのか喫茶店カレーなのか、お子様カレーもあるか…提供方法や器、トッピングもいろいろ。
オーソドックスで誰でも食べやすいものもあれば、個性的で食べる人を選ぶようなものもある。
ボルダリングジムも、似たところがあるかもしれません。
どんな違い・個性があるのか、少し深掘りしてみますね。
▼「ボルダリング」で検索!
もくじ
ジムごとの課題に「個性」が出るポイント
ジムの課題は、いろんな要素が入り混じってジムごとの個性が出てきます。
その中の一部の要素について書いていきますね。
壁の違い
【傾斜】
壁はいろいろな傾斜があり、一枚の壁が複数の傾斜壁の組み合わせでできていることもあります。
ジムにより建物の広さも違い、設置できる壁の枚数もいろいろ。
ジムによって設置している傾斜や形状もそれぞれ異なり、課題傾向が左右される大きな要因となります。
- 坂道のように向こう側に少し倒れる形で傾斜のある「スラブ壁」
力が弱くても登れるため初心者やお子さんでも楽しみやすい反面、上級課題だと小石のように小さなホールドが付いていて持ちにくく乗りにくく、バランス感覚や足の使い方の技術を要求される壁でもあります。パワー系の男性などは苦手な方も多い印象です。 - 床に対して垂直に立ち上がった「垂壁」
スラブと緩傾斜の中間どころの壁で、スラブよりは登る時に重力を感じます。足の使い方や重心移動が大事になってきます。 - 緩めの傾斜の「緩傾斜壁」
見た目にはそんなに傾斜があるように感じないのに、思ったより重力を感じます。スラブと比べると、バランスというより体幹を意識して使う必要性がより強まります。 - 傾斜の強い「強傾斜壁」
下への重力をかなりきつく感じ、「体幹や足を使っていかに身体が壁から離されないようにするか」など、パワー系の課題になってきます。この辺りからは力の弱い方や女性などは苦手意識を感じる人が増えてきますが、お子さんや細身の方など体重の軽い人は重力をそんなに感じないので、意外に苦にしないことも多いです。
傾斜が強まると小さいホールドではなく持ちやすいホールドが増えてはきますので、しんどいけどホールドが持ちやすいから好き!という人も。 - 床とほぼ平行の、天井のような「ハング壁」
地球にはこんなに重力があるのだ!と実感する壁。初めて見た方が「うわすごい!」と一目で難しい、キツイと感じる壁です。体幹と足の力をフルに使って下に落ちないよう、見た目そのままいろんな部位の力が必要です。
このように、課題で要求される力も壁の傾斜度によっても変わります。
【高さ】
壁の高さも、建物の天井高によりいろいろです。
4m以上の壁高を設置できる天井高の物件を探すのもなかなか難しいですので、天井高が低くそれに伴い壁高が低いジムもあります。
単純に壁高が高ければ登っていくほど足がすくむような恐怖感のある課題も増えますし、逆に低ければ比較的高さが怖くなくなることもあるでしょうし、例えばハング壁を使うことでパワー系の課題が多めになる、なんていうこともあるかもしれません。
それもまた、ジム毎の個性です。
【その他】
また、「ムーンボード」という世界共通規格で作られた壁が設置してあるジムもあります。
世界中で共通のホールドが決められた場所に付けてあり、専用アプリを使うことで世界中で共通の課題が登れる、という壁。
個人でも自作の課題がアプリを通じて公開できるので、課題数は無限。自分の課題を海外のクライマーが登ってくれたり、海外のクライマーが作った課題を日本のホームジムで登ることができる楽しさがあります。
LEDが点灯して課題のルートが分かるようになっているタイプのムーンボードもあります。
ホールドの違い
課題に使われているホールドの大きさなども課題傾向に影響します。
大きなホールドはダイナミックな動きを要求されるような課題になることが多く、小さいホールドは持つのにも足置きにも繊細さが必要で保持力を求められる課題が多くなる傾向があります。
なので、大きなホールドがたくさん付いているジムと小さめのホールドの割合が多いジムとでは、少し全体的な課題の傾向が違ってくるのです。
これはもちろんジムの目指す方向性 ― 保持系課題メインなのか、動きの大きなダイナミックな課題メインなのかなどによっても当然変わってくるだろうし、正直なところ単純に経済的なところも影響は大きいです。
ホールドは、大きければ大きいほどお高い…!眼が飛び出ちゃう…!
どっちにしても、各ジムのセッターさん(課題を作る人)は、使うことのできる限られたホールドの中から、登る皆さんのことを考えながら心血注いで課題を作成します。
ジムのコア(メイン)利用者層/ジムにとって増えてほしい利用者層
たいてい課題は、そのジムを一番多く利用している、いわゆるそのジムにとって多く利益を生んでくれるコア利用者層にまずはフォーカスして作られていることが多いと思います。
次いで、「これから増えて欲しい層」も意識します。
ジムにより、それぞれ以下のような層に対して考慮してあることが多いのではないでしょうか。
- 競技選手
競技大会に対応できるような課題、例えばいくつかのホールドの上を走って次のホールドに飛びついたりするような身体の連動性が求められるコーディネーション課題や、一般クライマーには太刀打ちできないようなものすごく強度の高い課題が多く設定してあったりします。 - 外岩クライマー
外岩を登るトレーニングになるような「保持系」課題が好まれますので、ジャンプしたり走ったりよりもしっかりと指や身体を使いホールドを保持する力や基礎的な身体の使い方が要求される、いわゆるクラシカルな課題が中心に作ってあったりします。 - キッズ・初心者・女性
小学生を中心にキッズスクールの生徒さんなどの多いジムは、いわゆる「リーチ」が小さめに設定してある課題が多めかもしれません。キッズだけでなく初心者の方や女性もとっつきやすいように、初級課題の数が多めに充実させてあったりも。 - フィットネスやレジャー目的の人
いわゆる「ガチ」というよりは、たまにビジター利用する人でも軽めに楽しめるよう、初めてでも登りやすい易しめの課題の数を充実させているところも。
オーナー・セッター(課題を作る人)の考え方の違い
今まで挙げたような要素を総合して、ジムオーナーの方針がどうなのか。
またその方針をもとに、セッターがどう課題を作っていくか。
それがジム全体の課題のタイプや難易度の印象を作り上げます。
例えば『これから始める人や初心者の人』に対する考え方として、
・比較的登りやすい課題を多く設定することで、“ボルダリング“に対する敷居を低くし、たくさんの方に「ボルダリングって楽しい!」と思って続けてもらえるような課題作りを心掛ける
・難易度が低めの級設定の課題からしっかりと身体の使い方などを習得できるよう、低難易度からムーブやホールドの持ち感にこだわった課題作りを心掛ける
こんな違いだけでもジム全体の課題の印象に関わってきます。
『クライミングの楽しみ方』に対する考え方として、
・競技にもどんどんチャレンジしてほしいし、コンペも開催して、最近のコンペの課題傾向を体感してほしい
・外岩クライミングLOVE!うちのジムでしっかり外岩のトレーニングして臨んでほしい
・趣味ながら上達もしてほしいし、真剣に楽しくクライミングに取り組んでほしい
・仲間作り・友達作りもしながら、ワイワイ気軽に楽しんでほしい
たとえばこんなことも、全体の課題傾向の方向性にかかわる大きな要素です。
クライミング・ボルダリングに対する考え方・関わり方は本当に人それぞれで、それがジムの課題傾向や個性として現れます。
「楽しい!」「成長できる!」と思えるジムと出会えますように
このように、一口に「ボルダリングジム」といっても課題の個性は多種多様。
なので、特にジムの選択肢が多い地域の方は、一か所行ってみただけで「ボルダリング、いまいちだったなぁー」と思ってしまうのは早計過ぎ。もしかしたら、別のジムで「あれ、面白いぞ!」と感じることがあるかもしれません。
実際に私が働いているジムでも、「違うジムに行ってみたことあるんですがいまいちハマれなくて…こっちは楽しいです」と言われたこともありますし、多分、というか絶対に、その逆もあります。
初心者の方やお子様の中でも、
「難易度が低い課題が多いとハードルも低くて楽しいし、たくさん登れる課題があって自己肯定感も上がり、モチベーションが維持できる」
「難易度が高い課題が多いジムだけど、それに挑戦して登れた時の嬉しさは格別。早い段階で技術を身に付けられるし自分が成長できるから楽しい」
といったように、個々で感じ方も違います。
どちらの考え方が正解とか、良し悪しはありません。それが自分の感じ方なだけ。
そのようなところも踏まえて、皆さんが自分の感性に合う「通ってて楽しい!」と思えるジムと出会えることを、心から願っています。
\ボルダリングジムもたくさん載ってます!/