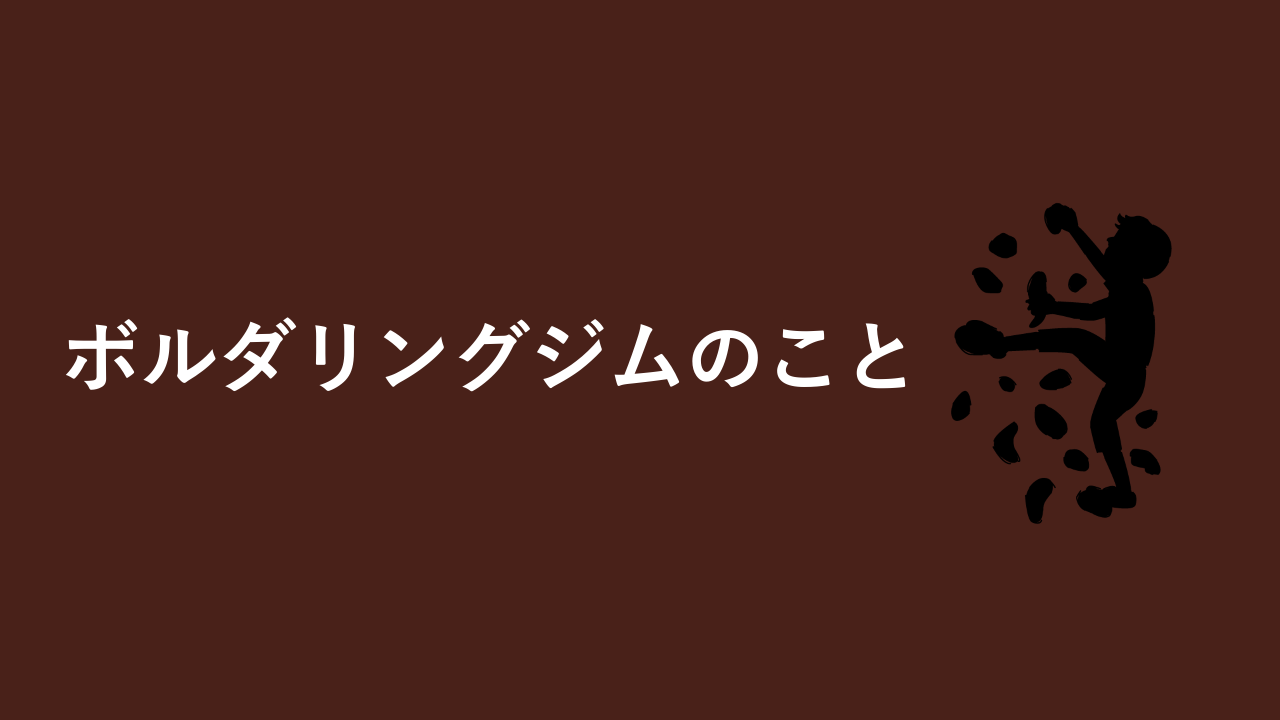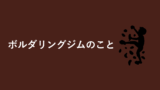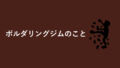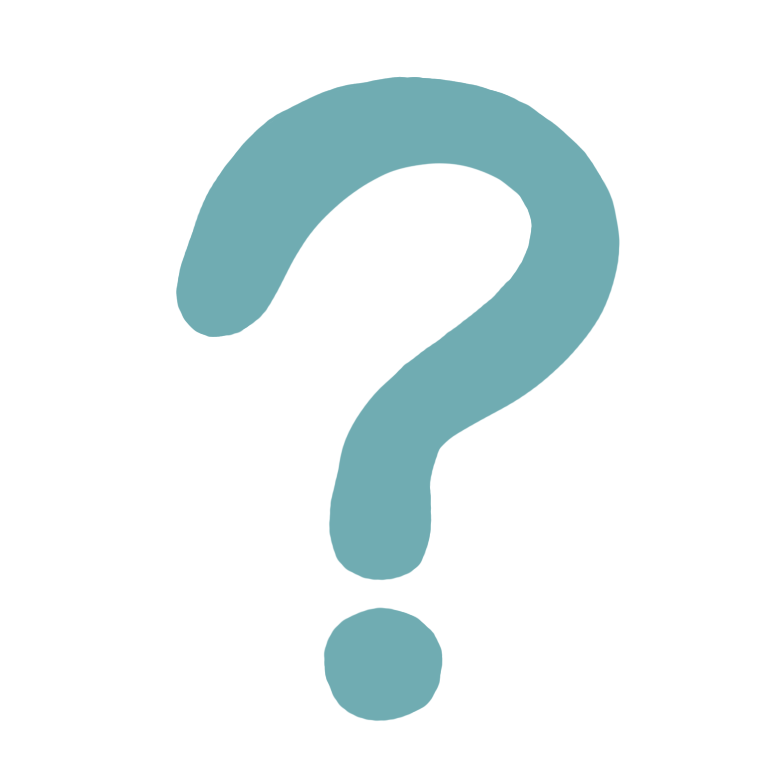
- ボルダリングジムには”難易度”によってルートが設定されているって聞くけど、具体的にどういうこと?
- どこのジムでも共通の難易度なの?
- ジムが「甘い」「辛い」ってどういうこと?
『ボルダリングジムには、「初めての人が登れる課題」から難易度によって課題(ルート)が配置されている』
各ボルダリングジムのホームページ等にそんな風に記載されていると思います。
なんとなく、分かったような分からないような…
なんかピンと来ないなという方も多いのではないでしょうか。
その辺について、もう少し詳しくお話ししますね!
▼「ボルダリング」で検索!
もくじ
ボルダリングの難易度の指標
日本のジムでは、「級」「段」という指標を使い難易度を表すことが一般的です。
ピアノや書道などでも使いますよね。
「級」という表記は日本独自のもので外国ではまた表記が変わります。中には外国と同じ表記を採用しているジムもあるかもしれませんが、ほとんどのジムで「級」を採用しています。
壁には、あらかじめホールド(石)を設置し登る課題(ルート)がセットされています。
ジムによって「○級はピンク、○級は緑」などと基準が設けられ、その課題ごとにカラーテープなどを貼って「級」が分かるようになっています。
例えば、ピアノなどのようにテストを受けて合格するとグレードが上がっていく、という方式ではなく、自分で「今日は○級の課題を登ろう!」と好きに選んで登ります。
今打ち込んでいるのは5級だけど今日は6級を全部もう一度丁寧に登るんだ、とか、アップにまずは8級から順に登って今日は初めて4級に挑戦してみよう、とか、自分の自由意思です。
中には10級や9級から設定のあるジムもありますが、たいてい8級からスタートするところが多いのではないでしょうか。
7級・6級・5級…と数字が小さくなるにつれ課題が難しくなっていき、1級までくると次は「初段」になります。(初段=1段)
「段」は数字が大きくなるにつれ難易度が上がります。
「級」や「段」は、ジムによって基準が違う
実は、級や段については、ジム毎に体感はまったく異なります。
全国で共通のものではありませんし、「○○ができたら○級」というような明確な基準があるわけでもありません。
あくまでそのジムの中での基準により設定されるものになります。
例えばピアノでいうと、カワ○とヤマ○ではグレードの基準は異なりますよね。「カワ○で6級」というのと「ヤマ○で6級」というのとでは技術の到達度はたしか少し違うはず。
それはこのふたつの会社がグレードの共通基準を設けてなく、それぞれの会社の中での基準で実施しているからです。
ボルダリングにおいても、級を決める基準はジム毎に違います。
ジム毎に壁の傾斜も使っているホールドも違い、何よりオーナーやセッター(課題を作る人)によっても課題傾向や級に対する考え方が違います。
ある人がホームジムでは2級を登るけど、遠征先のジムの5級が登れない…なんていう現象もザラに起こるのです。
これは、ジム毎の個性の違いを楽しむ一つの要素になっていて、「あのジムは甘い」「あのジムは辛い(からい)」などという言い方をしたりします。
ジムの課題の個性についてはまた別記事でも深掘りしたいと思います。
足自由・足限定
課題の難易度が変わる要因のひとつに、「足自由」と「足限定」という要素があります。
- 「足自由」
手はその課題で指定されているホールドだけしか使えないが、足を置くのはどれでも自分で好きなホールドを使ってよい - 「足限定」
手も足も課題で指定されているホールドしか使えない
ほとんどのジムで、7・6級くらいまでの初級課題が足自由、そこからだんだん足限定になっていくことが多いと思います。
中には、ある課題を足自由で登ることで8級、同じ課題を足限定で登ることで6級とする、というような方法を採っているジムもあるようです。また、8級から足限定のみというジムもあります。
それらもまた、それぞれのジムの個性です。
どのように課題を選んだらいいの?
前述のように、基本的にはどんな級でも自分が好きな課題、登りたい課題を選んで登ればいいです。
とはいえ初めてでいきなり難しい課題に挑むのは、モチベーションの上でも身体の負担を考えてもあまりおすすめできません。
初級課題から少しずつ少しずつ難易度を上げていくほうが、筋肉も少しずつ付き、経験値も増え、何よりも動きに慣れてムーブが身に付いてくるので、無理のない身体の使い方で登れるようになります。
まだ身体のできていないうちに必要以上の力を使って負担をかけ続けると、結局上手く登れないだけでなく故障につながる恐れも。
同じ級の中でも、壁の傾斜が違ったり、想定ムーブが違ったり、もちろん使ってあるホールドも違います。
セッター(課題を作る人)は、この課題を登ることでこんなムーブを習得してほしいな、この壁・このホールドを経験してほしいなといろんな想いをひとつひとつの課題に乗せていますので、皆さんにはぜひ、あなたにとって易しい級だとしてもいろいろな課題を登ってみて欲しいなと思うのです。
「級」はあくまで目安 それにこだわりすぎないで
ジムスタッフをやっていると、「ホームジムでは2級登ってるのに、ここでは登れない!理不尽だ、こんなの良くない!」なんてちょっとお怒り気味に言われたりすることが実際にあります。
そういう人って多分、課題そのものの内容や質よりも「自分は○級が登れる」というところに主に価値観を置いてしまっていて、「級」に振り回されちゃってるんだろうなと思うんです。
「ほう、ホームジムの○級とこのジムの△級が同レベルくらいかな、なるほど」と違いを楽しみながら登ればいいだけのこと、なんですよね。ほんとは。
「級」はその人のボルダリング能力に対する評価や価値では無いのです。あくまでジムの中で便宜的に難易度を示している目安。
その人の得意不得意によっても感じ方は変わってくるものだし、課題の本質ではありません。
もっと、その課題がどんな壁に付いていて、ホールドの持ち感やムーブはどうか、自分にとって得意なのか不得意なのか…などなど、課題そのものの質や内容にぜひ意識を向けてみてください。
\ボルダリングジムもたくさん載ってます!/